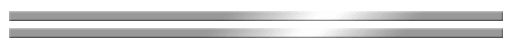
ハスラー(MR-92S)のナビ・無線機と車中泊装備などのDIY

| 10年物のハスラー(初代)を更新することになり次もハスラーになりました。 DIY作業は ・ナビ(運転時操作対応)とバックカメラ取付け ・ドラレコ(後方カメラあり)取付け ・ETC取付け ・無線機搭載 ・一人用車中泊ベッドなど です 出来たところまでご紹介しています。 *内装の外し方はYoutubeに色々掲載されていますので省略しています ナビゲーション、ドライブレコーダ、ETC取付け |
コントローラ増設の方法が決まったのでFT-857DMを設置しました。
アンテナ基台を増設しリグごとに専用化しました。
FT-8900(29/50/144/430FM)とFT-857(HF〜430全モード)の同時運用ができるようになりました。 FT-8900減電圧対策用の簡単なサブバッテリー
|
車中泊用のベッドとカーテンなど .
| 車内左側にニトリの8cm厚マットレスを設置しました。 下に板を敷いているので凹凸はありませんがシートバックテーブルのため助手席の背付近が少し高くなります。 またテーブルの幅より外側は支えられないので、現状は真ん中辺で寝ることになります。 改善した記事は→こちら |
|
| マットレスの下に敷いた3枚構成のベッドベースです。 先代ハスラー用に作った後方側の板に切り欠きを追加工して流用しています ←画面をクリックすると寸法図を表示します |
|
| ベッドベースは助手席の幅なので、ベッドをセットしたままでも無線機が使えます。 | |
| 目隠しのカーテンはマグネット固定式を3組(6枚)購入しました。 前ドアとリアハッチ用計4枚は固定方法と幅を足すため下の100均カーテンを接続して作ります。 フロントガラス部は夏に使っているサンシェードで十分なのでカーテンは用意しません。 |
|
| ダイソーの吸盤付き車用カーテン(小)を縦半分に切ったもので、上端の左右に引っ掛け用の金具(前かん)を縫い付けてあります。 (前かんが車外側になります) 切った状態の4枚が必要です。 マグネットカーテンは上端合わせで前カン面に3〜4cm重ねて設置時に小カーテンが車前方になるようにマジックテープで接続します. |
|
| 前かん部分です。 内装の樹脂パネル上端やウエザーストリップの隙間に上手く刺さります。 |
|
| 100均で購入しました。 受けの方は使いません。 |
|
| 使用状態のカーテン(左側前ドアおよび小窓〜リアハッチ用)です。 白く見えているのがマジックテープで、3か所でつないであります。 右側用は前かんのついた小カーテンをマグネットカーテンの右側に連結します。 |
|
| Bピラー付近から後方のカーテンです。 小窓の所は前後の内装の隙間に小カーテンのフックを掛けて止めています。 車中泊時は吊り金具にLEDライトを引っ掛けられます。 |
|
| 前方のカーテンとサンシェードです。 小カーテンの前側フックはサンシェードに掛けてあり、ドア側は使わずに大カーテンのマグネットで持たせています。(サンシェードのサイズにより掛ける位置を調整) 日が当たっていてサンシェードの脇が透けていますが、小カーテンでカバーされているので車内が暗ければ外からは見えません。 |
|
| ハンギングランプ等に使う吊り金具で、現在3か所に取り付けてあります。 先代ハスラーより取り付けられる穴の数が減ってますね。 写真はフックを降ろした状態です。 |
|
| 使ったのはこの部品。 先代ハスラーから移設です。 |
|
ラゲッジボード製作 .
| 定番サイズのラゲッジボードを製作しました。 棚板はパイン集成材 1200x300x18mmから切り出し。 長さ1200mmの材料は置いているところが少ないですが、幸いロイヤルホームセンターで入手できました。 |
|
| 棚受け部材一式です。 L金具 50x50x25 t3 六角穴付きボルト M3x15 黒 平ワッシャ M6x20φ 黒塗装 六角ボルトM6x15 ノブスター M6 鬼目ナット M6x10 |
|
| L金具の車体側に隙間テープを貼り付けました。 内装への傷を軽減する目的ですが、薄いので気休め程度です。 |
|
| 棚受けのL金具は六角穴付きボルトM6x15で組付けました。 L金具は上下に動かせますがボルトに当たるまで下げた位置が安定です。 ワッシャはM6用外径20mmをスプレーで黒塗装したものです。 |
|
| つば付きねじ込み式の鬼目ナット(L=10mm)を現物合わせでL金具固定ボルトと離れた側に取付けます。 下穴は9φx10mm、板厚が18mmですので貫通させないよう注意です。 |
|
| ノブスター付の六角ボルトM6x15で棚板を固定しますので取外しは容易です。(写真は右側、左側も同様) 今のところガタつきはありません。 |
|
| 仮組みしたラゲッジボードです。 棚下は36.5cm(実測)あり手持ちのクーラーボックスが収まります。 |
|
| 棚板にニス塗りして完成。 普段は後席と棚板の間にベッドベースとサンシェードなどを立てて収めています。 |
車中泊設定の車内 .
| 就寝用にセットしたベッドとラゲッジボードです。 マットレスは上に乗って動きやすい様に固めの物を選んでいます。 |
|
| ベース部分が平らなので、厚いマットレスでなくこんなマットでも凸凹は感じません。 ベッドベース3枚と一緒に荷室に収納できるので4人乗車でも邪魔なりません。 |
|
| 前方のマットレスを折り返してから下の板を抜けば簡単に後席側に移すことができ、助手席を使うことができます。 |
ベッド支持方法の改善
これらの積み方は今後の課題になります。 |
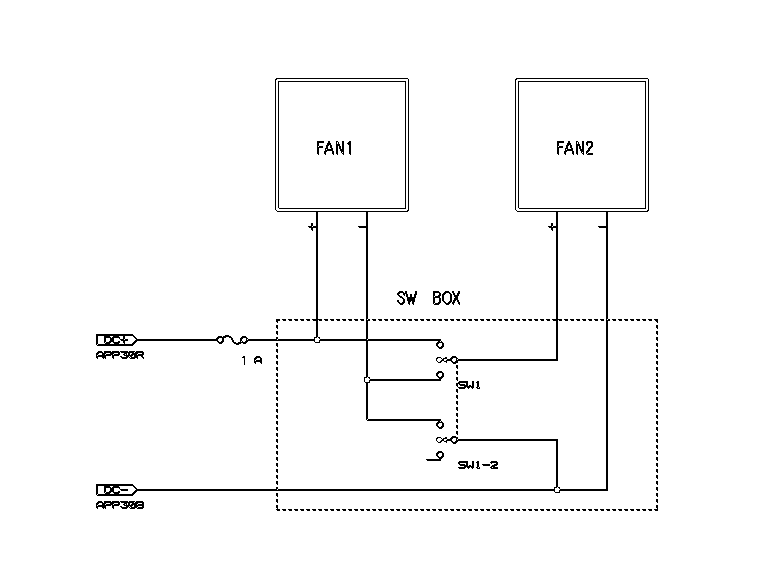
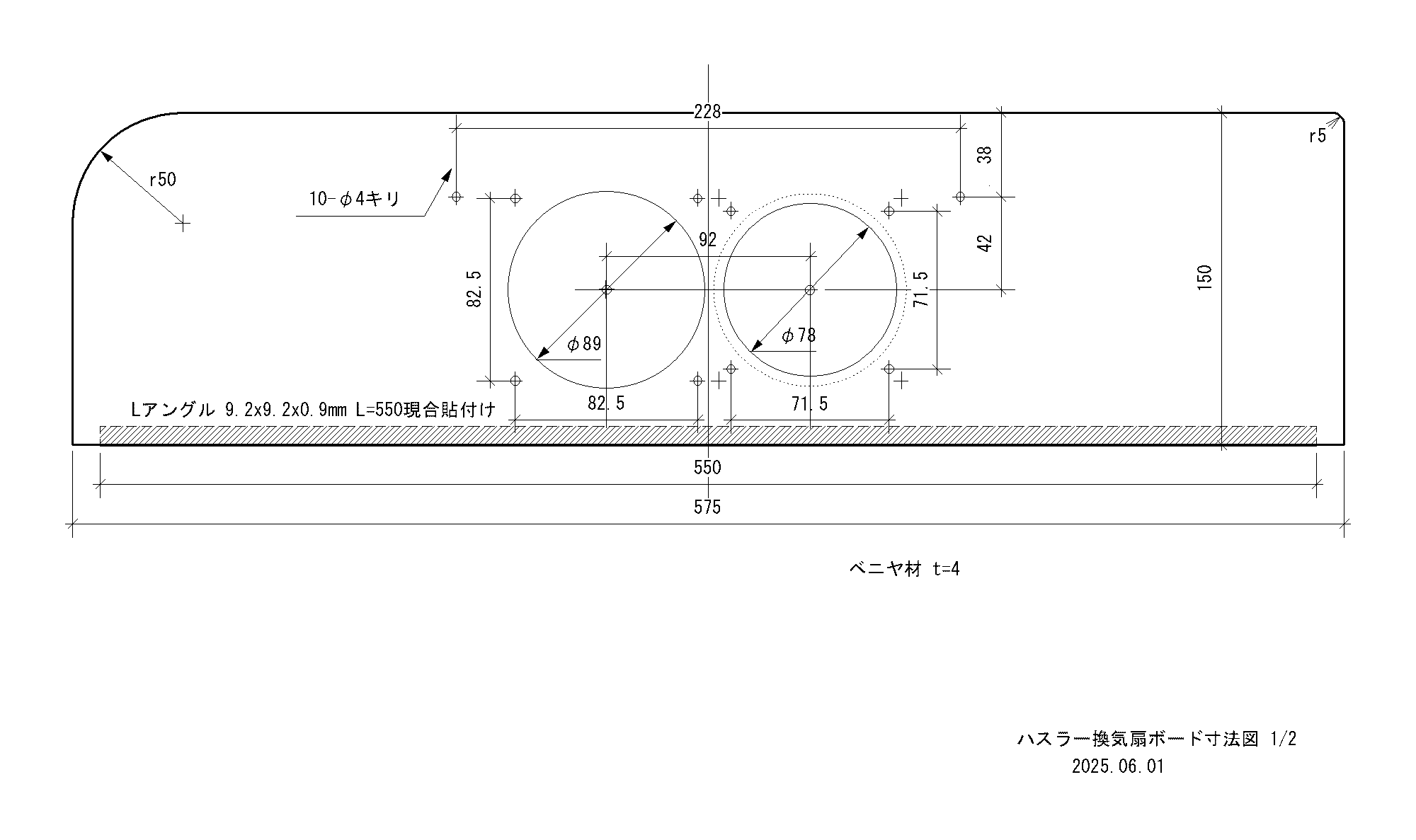
 トップページへもどる
トップページへもどる